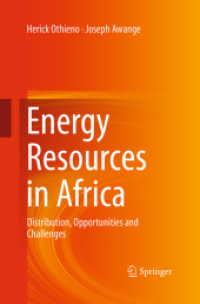内容説明
『マンホールのふた』の著者・林丈二が明治へタイムスリップ。開化の蓋を開いてみたら「日本のいま」も見えてきた。明治の新聞挿絵を“路上な目線”で観察する。
目次
文明開化といえば散切り頭
女髪結いは何ら変わらない
縁側で髪を洗う
夏の来客のもてなし
待合の帽子置場
氷店の季節
雨の日の拵え
長屋の子守娘
貧乏と病人
貧乏の中のゆとり〔ほか〕
著者等紹介
林丈二[ハヤシジョウジ]
著述家。エッセイスト。明治文化研究家。路上観察家。1947年東京生まれ。武蔵野美術大学卒業。大学生のときにマンホールの蓋に注目、以来、日本をはじめ世界中のそれを観察し、『マンホールのふた(日本篇)』『マンホールの蓋(ヨーロッパ篇)』にまとめる。「路上観察学会」発足時には、発起人の一人として参加。近年は、若手建築家や建築を学ぶ学生を中心に結成された「文京建築会ユース」とのコラボによる町歩きや展示なども行なっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ちさと
29
維新後に日本に入ってきた西洋文化を、不自然ながらも少しずつ生活に取り入れていった日本人。着物の下にシャツを着てたりお洒落に帽子をかぶりながらも帯刀してたりといった様子を、明治時代の新聞挿絵から覗き見する本です。華やかなイメージの文明開化ですが、恩恵を受けたのは生活にゆとりがある人たち。この時代庶民の生活はまだまだ江戸時代そのもので、東京に住む9割は貧乏人だった。庶民の身の回りでの文明開化の物品は挿絵を見ても髪型くらいなものでとても少ない。「呼吸器」として一般にマスクが売り出され流通していたのには驚き。2019/01/12
マッピー
13
新聞の挿絵を基に、明治の世相を解説。これが愉快。明治の男性はちょん髷を切って頭が寂しくなったせいか、よく帽子をかぶっていたとか、防寒を兼ねて着物の中にシャツを着るのが流行ったとか、着物は袖や裾を手で押さえなければならないことが多いので、日本人はよく口でものをくわえるとか、目の付け所も面白いです。そして妙に、貧乏人や病人や犬がリアル。これは身近によく見かけることがあったからなのか。近くて遠い国のような明治時代。面白いなあと思う反面、どうして簡単に忘れてしまったのだろうとも思う。2018/03/09
猪子
7
ものすごく勝手に『チョビ助』が猫のキャラクターだと思って読みはじめました。全くそんなことはなかったし、なんでチョビ助は猫!って自分で決めつけちゃったのかも分からなくて怖い。明治の新聞挿絵から読み解く江戸〜明治の日本の暮らし。面白かったです。2022/05/14
こぶた
6
★★★ 文明開化ネタばかりでなく、文明開化がやってきた時代の生活ぶりを挿絵から読み解くというもの。浮世絵の背景を説明するのは見たことがあるけれど、挿絵新聞の挿絵というのははじめて。読むのは楽しかったけれど、調べるのはとても地味な作業だし、当時の文語みたいな文章は読みにくいと思うのにすらすら読まれている感じで、樋口一葉などにも精通されていて、作者の知識すごし、と思いつつ、サラっと楽しんで終わり。2022/09/02
hitotak
4
明治時代の新聞挿絵をもとに当時の風俗を読み解く。連載小説の挿絵は、室内の置物や階級や貧富の差により違う着付け、履物などがこまごまと書かれていて、現代ではなくなったもの、もはや何に使っていたのかすら不明なものなどもあって面白い。首元にハンカチを巻くのが流行し、西洋人が呆れていたとか、西洋のものへの憧れは強くあるが、知識がないゆえの間違った使用法なども多かったのかな。新聞投書には挿絵画家ファンからのものもあり、某日のあの絵はよかったとか手抜きだとか好き勝手言ったりと、ファンの習性は今と変わらないようだ。2018/11/25